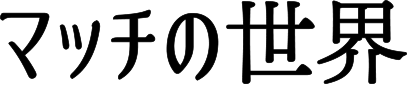マッチ対談
HOME > バーチャルミュージアム > マッチ対談 > マッチ・ト・ラベル
- ゲスト矢野 正博(ジャズルーム「吐夢」オーナー)
- 聞き手加藤 豊

【ゲストプロフィール】
東京・阿佐ヶ谷のジャズルーム「吐夢」、ブラックミュージック系の「鈍我楽」などのオーナーであり、60~70年代のJAZZ喫茶マッチのコレクターでもある。
Jazz&Culture 阿佐ケ谷不届記:http://adobensya.jp
 加藤
加藤私が蒐めているのは商標マッチ(商品として販売するマッチ)なんですが、本日は矢野さんが蒐めていらっしゃる広告マッチに入るJAZZ喫茶のマッチコレクションを拝見させてもらいます。 このコレクションのファイルは凄いですね~。全国津々浦々のJAZZ喫茶マッチ。まず都道府県ごとに分けられていて、東京都内は区別にも分けられている。これは全部ご自分で現地に行かれたJAZZ喫茶なんですか?
僕は旅人なんですよ(笑) 若い頃から日本全国、貧乏旅行をしながらその土地土地のJAZZ喫茶を訪ね歩いて行くという。 まるで、旅の僧にとっての宿坊のように、一夜の宿を戴いたこともありました(笑) 巡礼の地を訪ねて行ったその証としてマッチを戴いてきているうちに・・・。
その足跡を僕のマッチコレクションの一部としてネット上でも公開しているんですが、そのタイトルは「マッチ・ト・ラベル」(笑) マッチラベルと旅をひっかけてね。 JAZZ喫茶マッチは旅をする僕にとってある種の通行手形だったのかもしれないですね。
 矢野
矢野 加藤
加藤なるほど!このマッチラベルのコレクションがそのまま矢野さんの旅の記録なわけですね。
そう。僕が20代から最後は36才くらいまでの旅の記録だね。 見知らぬ土地のJAZZ喫茶に入って、最低3つマッチをもらうわけですよ。 自ら使う為・コレクション用・交換用と、どうしても3つは必要なんです。 ただ、3つくださいと言うと、これが嫌がられましてね~(笑) 気難しそうなオーナーが多かったから、言い出しにくくて(笑) でも、僕がわざわざ東京からやって来たということがわかると、だんだん打ち解けてくれて、いろいろ情報交換やら、地元のこととか教えてもらえることも多くて。
 矢野
矢野 加藤
加藤マッチ自体、ある時代を象徴するアイテムなんですが、特に「広告マッチ」はその時代時代の様子がとても良く見えますよね。その時代の流行とか雰囲気とか・・・
まさにそうですね。 見ているだけであの時代の匂いがしてくるというか、あの混沌とした時期のストーリーが蘇ってくるのも視覚からくるマッチの力かもしれないですね。
 矢野
矢野 加藤
加藤お店のマッチというのは、当時重要な広告媒体であったわけですけど、単に宣伝というだけでなくて、ステイタスというか、プライドというか、存在価値というか、そういう位置づけでデザインにも情熱と愛情を傾けていたお店も多かったんでしょうね。
JAZZ喫茶のマッチは幅広の平型マッチが理想的なんですよね。つまりLPジャケットに近い比率のサイズなんですよ。だから、JAZZ喫茶のオーナーもミニレコードジャケットを作るようなつもりで自分の店のマッチのデザインを考えるわけだから、力が入るんですよね。当然もらってきた客の方もそれを部屋に並べたくなるっていうか(笑)
 矢野
矢野 加藤
加藤ああ~っ!なるほどね!そうか、LPと同じ比率ということでね。 単なる広告マッチというよりもっとその意識価値は高かったわけですね?作る方も貰う方も。
だから、お店に置いておきながらも、実はあまりあげたくないっていうか(笑) 大切に使ってくれるならいいけど、いい加減にされるくらいならあげたくないっていうくらいの。ま~、実際にはコストもかかっているわけだし。 当時、マッチ発注のロットが5,000個、1万個だったので、費用もなかなか厳しいものがあって。(現在では、2,500個が最低ロット)
 矢野
矢野 加藤
加藤宣伝販促物といっても、チラシ感覚ではなくて、高いパンフレット感覚のような?
そう、そう(笑)
 矢野
矢野 加藤
加藤そうか!、だからこうして沢山のJAZZ喫茶マッチを見ていても、どれもこれも魅力的なんですよね。
JAZZ喫茶においてマッチの重要性は他にもあるんです。 JAZZ喫茶ではライターが使えなかったんですよ。あの場では絶対にマッチでなければいけなかった。
 矢野
矢野 加藤
加藤エッ、それはどうして?
JAZZ喫茶という独特の空間では、みんなじっと静かに音楽に浸っているわけで、あまり話なんかもできない雰囲気。まさに「スピークロウ」だね(笑) だからそういう場ではライターはもってのほか。ライターの蓋を開けるピン!という音とか、火をつける時のカチンという金属音を立てると、まわりの客から睨まれる(笑)だからみんなマッチしか使わない。マッチを擦る時のシュッ!という音はJAZZに馴染めてたようで。 それに、音楽を聞きながらマッチの火を見つめているのも、あれがなんともいいんだな~。 瞑想みたいな感じでね。
 矢野
矢野 加藤
加藤そうそう。僕も大学当時、1年ほどJAZZ喫茶に通っていたことがありましたが、とにかく話ができないんですよね。つい聞きたいこととか、話したいことが出てくるんだけど。それをじっと我慢しているのが辛くなって、JAZZ喫茶通いから脱落してしまったクチなんです(笑) 当時はJAZZ喫茶、クラシック喫茶、ロック喫茶、ラテン喫茶、歌声喫茶とか、いろいろな喫茶店があって、それぞれそこで音楽を聞いたり、情報を得ていたりしていたんですよね。今の喫茶店とはかなりイメージが違いますよね。
まさに60~70年代はコーヒー文化、喫茶店文化全盛でしたね。 若者は酒場に行くよりコーヒーを喫茶店に飲みに行く方が文化的というか、カッコいいというか(笑)喫茶店は様々なカルチャーの人々が集まる場所で、あらゆる文化や情報はそこから発信されたり収集されたり。ある意味、あの時代の起爆剤的存在だったんじゃないかな? だから、大人達から喫茶店に行くような学生は不良だというレッテルを張られていた。
 矢野
矢野 加藤
加藤今ならインターネットで簡単に手に入る情報も、昔は自分の足で出向いて、情報を持っている人達と交流しなければ手に入らない時代だったから、そういう意味でも重要な場所だった。
マイク・モラスキーという知人が、日本のジャズ喫茶の研究をしていてね、彼がいうには、日本のジャズ喫茶は寺子屋だと(笑)アメリカには無い非常に日本独特な文化なんだよね。
 矢野
矢野 加藤
加藤なるほど(笑)喫茶店のオーナーと客の関係は、教師と生徒に似た特殊な関係が内在していたわけですね。そこに通い詰めることによって、若者はジャズとかアメリカンカルチャーを学んでいったわけだ。あの当時の人権問題、反戦運動といった社会的問題も含めてね。
そう。エネルギーに満ちた<文化の拠点>的イメージだね。 だから、ジャズ好きということにプライドを持っていたよ。特に「モダンジャズ」を聞いているっていうことにね。モダンジャズでなきゃダメなんだよ(笑)
 矢野
矢野 加藤
加藤矢野さんが最初にJAZZに興味を持ったのはいつ頃なんですか?
16才の夏休み。高校の先輩にJAZZ喫茶に連れていってもらったのが最初で。 新宿の「DIG」というお店。 最初もうドキドキしてね・・・ その時、チャーリー・ミンガスの「直立猿人」と「原爆許すまじ」っていう曲が流れていて、「わぁ、この曲は何て言う曲なんだ?!」という衝撃と、同時にそのお店のマッチデザインになっているビュッフェの絵も鮮烈で。 それらがもう恐ろしいセットで強烈に脳裏に刻まれてしまって(笑) これが僕のジャズ初体験であり、その後の出発点なわけだから、この「DIG」のマッチは僕にとってはとても特別なマッチなんですよ。
 矢野
矢野 加藤
加藤「DIG」のマッチだけでもこれだけあるんですね。すごい!。 あれ?この白いスペースにメモ書きされているのは?
その時に流れていた曲とかをマッチにメモったりしていたんだよね(笑) 「DIG」のマッチを入れる専用ボックスは友人が作ってくれたんだよ(笑)
 矢野
矢野 加藤
加藤矢野さんのコレクションを拝見してそれぞれのマッチデザインを改めて眺めてみると、モノトーン調、いわゆる黒をベースに白抜き文字というのがジャズを想い描くデザインパターンのような気がしますね。だからこそ、そこにブルーやグリーンの色がうまく配色されてると意外に引き立って記憶に残る。 例えば、エアジン(神奈川)のモンローのマッチは、モンローも素敵でいい上に、店名のグリーンがとってもビビットな感じがしますね。
マリリン・モンローをマッチのデザインモチーフにしているお店もいくつかあるよね。 やっぱりジャズと言えば60年代。そして60年代のアメリカの象徴と言えば、マリリン・モンローってことなのかな?(笑)
 矢野
矢野 加藤
加藤マッチと歩調を合わせるようにジャズ喫茶自体も減少の一途を辿っているのですか?
残念ながらそうなんだけど。 でも、ここ数年は今も全国で600~700軒のJAZZ喫茶(ライヴハウスも含めて)が頑張っていますよ。 僕にとって「マッチ」とは、旅と出逢いとそして熱き想いをひっくるめて、あの時代の生き証人みたいなものだね。
 矢野
矢野