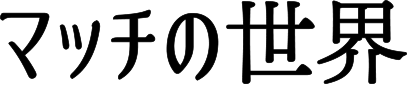マッチの歴史
HOME > バーチャルミュージアム > マッチの歴史 > マッチの黎明
人間と動物の違いは、火をコントロールできるか否かといわれている。しかし、昔から火をつくるのには苦労している。わが国では、明治の初めまでは火打ち石が主な発火方法であった。
欧州では1780年頃パリで黄りんを用いた「エーテルマッチ」が市販された。また、1786年に硫黄を軸木につけ、小瓶に黄りんを入れたマッチが市販されている。硫黄や塩素酸塩、ロジン等と濃硫酸を利用した浸酸マッチは1805年に発明されたと伝えられている。現在のマッチのように主薬に塩素酸カリを使用した摩擦マッチは1827年イギリスのジョン・ウォーカーが発明し、1829年にサムエル・ジョーンズが企業化し、「Lucifers」(和名リュキヘルス)と名づけて市販した。頭薬に黄りんを含み発火しやすい摩擦マッチは、1831年フランスのシャルレス・ソーリアによって作り出され、小箱に赤りんを塗布した安全マッチは、1855年にスウェーデンで発明された。
わが国では、宇田川榕菴(ようあん)が天保8年(1837)に欧州の文献を参考に化学書『舎密開宗』(せいみかいそう)を著したが、その中にマッチについての記述がある。かなり早くからマッチが紹介されていた。天保10年(1839)に讃岐高松藩の久米栄左衛門通賢(みちたか)が藩主松平頼恕(よりひろ)に命ぜられてマッチを試作した。これは、水戸藩主斉昭(なりあきら)が入手したリュキヘルスを模したつもりが、塩素酸カリの代わりに当時の銃の撃発用点火薬である雷汞(らいこう)(雷酸第2水銀)を利用したので、雷汞の別名ドンドロから「ドンドロ付木」と称したが、現在のマッチのようにスムーズな着火は困難であったようである。
 川本幸民(こうみん)
川本幸民(こうみん)弘化4年(1847)に兵庫県加古郡横谷村(現在の三田市)出身の蘭学者川本幸民(こうみん)が黄りんを使ったマッチを試作して成功している。これには、江戸で西洋の擦付木(すりつげぎ=マッチ)が話題になって、金座の商人が「もしこのようなマッチが作れたら50両差し上げよう」と言ったので、化学者である幸民が必死に研究して完成し、座興で発言した50両を獲得したという。
日本で初めてマッチを工業的に生産し、マッチの始祖といわれている清水誠は、明治2年(1869)5月12日、パリに留学のため横浜港を出航している。
明治3年(1870)にフラオンと称する外国人が横浜でマッチの製造を企図したとのことであるが、くわしい資料は存在しない。明治8年(1875)に米国人のブラウァーが横浜でマッチを生産しているとの記事が当時の新聞に出ていたが、前述のフラオンとの関係等は明らかではない。