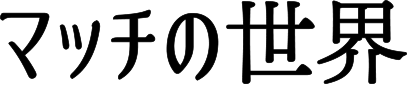マッチコラム
HOME > バーチャルミュージアム > マッチコラム > マッチと花火
夏の風物詩といえば、打ち上げ花火を思い浮かべることでしょう。ドドーン、と響きわたる轟音とともに夏の夜空に舞い上がる美しい光の競演には目を奪われてしまいます。
ただ、処によっては、冬の花火大会もあります。静岡県熱海市では今年で22回目となる冬の海上花火大会が催されています。冬の夜空は空気が澄んでいるので、より輝度の高い打ち上げ花火が見られるそうです。
夜空を彩る花火とマッチのことを思い浮かべてみると、マッチは、もとより火を付ける発火具、対して花火は火を付けた後は空高く打ち上げて鑑賞美を競い合うもの。
 神奈川新聞花火大会2010(撮影:吉岡 環)
神奈川新聞花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 神奈川新聞花火大会2010(撮影:吉岡 環)
神奈川新聞花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 横浜開港祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
でも、マッチも言ってみれば小さな火薬、マッチと大きな火薬玉の花火とは異母兄弟!?のような共通点が原料の面でいくつか見受けられます。
花火が盛んになった江戸時代は、原料として硫黄、木炭に加え、強烈な発火を起こすのに不可欠な酸化剤には硝酸カリウムが使われていました。ただ、この原料だと、燃焼温度が低いために赤橙系色の花火色に限られていました。低いとはいっても1700度もあるのですが……。このような花火は「和火」と呼ばれています。
その後、明治になり、西洋化学の導入により、明治12年頃、酸化剤として塩素酸カリウムが使えるようになったことで燃焼温度もおよそ2000度にまで上がり、輝度の高い色と明るさを出せるようになりました。
さらに、明治20年頃になると様々な炎色剤が使われるようになり、赤、黄、青、緑、紫、白など現在に見られるような明るく、カラフルな花火となりました。江戸の花火に対して「洋火」と呼ばれています。
横浜開港祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
でも、マッチも言ってみれば小さな火薬、マッチと大きな火薬玉の花火とは異母兄弟!?のような共通点が原料の面でいくつか見受けられます。
花火が盛んになった江戸時代は、原料として硫黄、木炭に加え、強烈な発火を起こすのに不可欠な酸化剤には硝酸カリウムが使われていました。ただ、この原料だと、燃焼温度が低いために赤橙系色の花火色に限られていました。低いとはいっても1700度もあるのですが……。このような花火は「和火」と呼ばれています。
その後、明治になり、西洋化学の導入により、明治12年頃、酸化剤として塩素酸カリウムが使えるようになったことで燃焼温度もおよそ2000度にまで上がり、輝度の高い色と明るさを出せるようになりました。
さらに、明治20年頃になると様々な炎色剤が使われるようになり、赤、黄、青、緑、紫、白など現在に見られるような明るく、カラフルな花火となりました。江戸の花火に対して「洋火」と呼ばれています。
 金沢まつり花火大会2010(撮影:吉岡 環)
金沢まつり花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 金沢まつり花火大会2010(撮影:吉岡 環)
金沢まつり花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 あつぎ鮎祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
あつぎ鮎祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 あつぎ鮎祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
あつぎ鮎祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 マッチ薬品標本:標本中、安全マッチの頭薬成分の瓶中に塩素酸カリウムが見てとれます。(所蔵:お茶の水女子大附属中学校)
塩素酸カリウムは、1786年にフランスのベルトレが発見しています。
この発見は、マッチの発明にも大きな役割を果たすことになり、1827年、イギリスの薬剤師ジョン・ウォーカーによって塩素酸カリウムを使った摩擦マッチが実用化をみます。その後、改良をかさね、現在のマッチ箱にこすって火をつける安全マッチとなりますが、今でもマッチ軸木の先には、燃焼剤である硫黄とともに塩素酸カリウムが使われています。
花火の色を出すには、金属や金属化合物が燃えた時に決まった色を出す炎色反応の性質を利用して花火の火薬に調合されています。
赤を出すには、ストリンチウム化合物、黄色は、ナトリウム化合物、緑色は、バリウム化合物、青色は、銅化合物、白色は、マグネシウムかアルミニウム、紫色は、炭酸ストロンチウムに酸化銅を加えたものを炎色剤として調合量を計りながら混合して作ります。
現在では、光輝剤としてマグネシウムやアルミニウムとマグネシウムの合金を使うことで燃焼温度が3000度まで高めることが可能となり、より輝く花火が見られるようになり我々の目を楽しませてくれます。
マッチも赤や緑の炎を出すことは可能で、炎色マッチとして海外で作られていますが、マッチ軸をこすった瞬間は一時、発色変化はしますが、一瞬の様で、すぐに普通の炎の色に戻ってしまいます。やはり、頭薬への調合量が微量であるために持続性を持たせるのは無理のようです。
そこで、花火のように火花がパチパチ散る変わりだねマッチを紹介しましょう。
「ベンガル・マッチ(Bengal Matches)」と呼ばれる、いわゆる「お遊びマッチ」で、パーティーなどで盛り上げたりする脅かしマッチの類い。普通のマッチのようにマッチ箱の側薬部にマッチ軸を擦ると一気に一瞬、赤や緑の炎色とともにパチパチッと花火のように発火します。
ただし、手許で火花を発する際に、燃えかすは飛び散るし、軸木は短いので、タバコを吸うとか火を灯すことは容易ではなく、ほとんど実用性のないものです。写真のものは、東ドイツ製のものですが、昔はイギリスでも作られていたようです。実際に使用してみると危ないこと、この上ありませんが、花火もどきの不思議なマッチといえるでしょう。
マッチ薬品標本:標本中、安全マッチの頭薬成分の瓶中に塩素酸カリウムが見てとれます。(所蔵:お茶の水女子大附属中学校)
塩素酸カリウムは、1786年にフランスのベルトレが発見しています。
この発見は、マッチの発明にも大きな役割を果たすことになり、1827年、イギリスの薬剤師ジョン・ウォーカーによって塩素酸カリウムを使った摩擦マッチが実用化をみます。その後、改良をかさね、現在のマッチ箱にこすって火をつける安全マッチとなりますが、今でもマッチ軸木の先には、燃焼剤である硫黄とともに塩素酸カリウムが使われています。
花火の色を出すには、金属や金属化合物が燃えた時に決まった色を出す炎色反応の性質を利用して花火の火薬に調合されています。
赤を出すには、ストリンチウム化合物、黄色は、ナトリウム化合物、緑色は、バリウム化合物、青色は、銅化合物、白色は、マグネシウムかアルミニウム、紫色は、炭酸ストロンチウムに酸化銅を加えたものを炎色剤として調合量を計りながら混合して作ります。
現在では、光輝剤としてマグネシウムやアルミニウムとマグネシウムの合金を使うことで燃焼温度が3000度まで高めることが可能となり、より輝く花火が見られるようになり我々の目を楽しませてくれます。
マッチも赤や緑の炎を出すことは可能で、炎色マッチとして海外で作られていますが、マッチ軸をこすった瞬間は一時、発色変化はしますが、一瞬の様で、すぐに普通の炎の色に戻ってしまいます。やはり、頭薬への調合量が微量であるために持続性を持たせるのは無理のようです。
そこで、花火のように火花がパチパチ散る変わりだねマッチを紹介しましょう。
「ベンガル・マッチ(Bengal Matches)」と呼ばれる、いわゆる「お遊びマッチ」で、パーティーなどで盛り上げたりする脅かしマッチの類い。普通のマッチのようにマッチ箱の側薬部にマッチ軸を擦ると一気に一瞬、赤や緑の炎色とともにパチパチッと花火のように発火します。
ただし、手許で火花を発する際に、燃えかすは飛び散るし、軸木は短いので、タバコを吸うとか火を灯すことは容易ではなく、ほとんど実用性のないものです。写真のものは、東ドイツ製のものですが、昔はイギリスでも作られていたようです。実際に使用してみると危ないこと、この上ありませんが、花火もどきの不思議なマッチといえるでしょう。
 ベンガル・マッチ:原料成分によって赤、緑、白色の炎が花火のように飛び散ります。東ドイツ製。
ベンガル・マッチ:原料成分によって赤、緑、白色の炎が花火のように飛び散ります。東ドイツ製。
 ベンガル・マッチのいろいろ:炎の色違いの各種。東ドイツ製。
ベンガル・マッチのいろいろ:炎の色違いの各種。東ドイツ製。
 パーティー用ベンガル・マッチ:パーティー用に販売されている東ドイツ製のもの。
パーティー用ベンガル・マッチ:パーティー用に販売されている東ドイツ製のもの。
 神奈川新聞花火大会2010(撮影:吉岡 環)
神奈川新聞花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 神奈川新聞花火大会2010(撮影:吉岡 環)
神奈川新聞花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 横浜開港祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
横浜開港祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 金沢まつり花火大会2010(撮影:吉岡 環)
金沢まつり花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 金沢まつり花火大会2010(撮影:吉岡 環)
金沢まつり花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 あつぎ鮎祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
あつぎ鮎祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 あつぎ鮎祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
あつぎ鮎祭花火大会2010(撮影:吉岡 環)
 マッチ薬品標本:標本中、安全マッチの頭薬成分の瓶中に塩素酸カリウムが見てとれます。(所蔵:お茶の水女子大附属中学校)
マッチ薬品標本:標本中、安全マッチの頭薬成分の瓶中に塩素酸カリウムが見てとれます。(所蔵:お茶の水女子大附属中学校) ベンガル・マッチ:原料成分によって赤、緑、白色の炎が花火のように飛び散ります。東ドイツ製。
ベンガル・マッチ:原料成分によって赤、緑、白色の炎が花火のように飛び散ります。東ドイツ製。
 ベンガル・マッチのいろいろ:炎の色違いの各種。東ドイツ製。
ベンガル・マッチのいろいろ:炎の色違いの各種。東ドイツ製。
 パーティー用ベンガル・マッチ:パーティー用に販売されている東ドイツ製のもの。
パーティー用ベンガル・マッチ:パーティー用に販売されている東ドイツ製のもの。