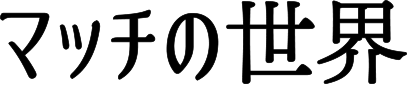マッチコラム
HOME > バーチャルミュージアム > マッチコラム > 苫小牧市博物館 「マッチワンダーランド」展覧会記
昨今、とみにマッチを見かけなくなった。使い捨てライターや禁煙ブームの影響は承知のことであるが、家庭内においても台所の自動点火電化製品の普及で徳用箱マッチも不要となってしまった。
そんななか、北海道の苫小牧市博物館においてマッチの特別展「マッチワンダーランド~歴史・デザイン・喫茶店文化~」が開催された。
苫小牧は明治末期に進出してきた王子製紙以前にはマッチ製造の原料として軸木用にドロノキ、小函用にエゾマツの製軸工場、小函素地(きじ)製造工場が数多く設立され、活況を呈していた。特に明治27(1894)年から明治40(1907)年頃は軸木、小函は半製品の状態で神戸へ移出してマッチに仕立て上げ、生産の80%は輸出用として神戸港から中国、韓国、インド、ロシアなど世界各地に販売されていった。
こうした明治の一時期ではあったがマッチ産業の底辺を支えていた苫小牧での展覧会開催は意義深い。
 苫小牧市博物館:苫小牧市文化公園の緑に囲まれた一角に昭和60年開館。
苫小牧市博物館:苫小牧市文化公園の緑に囲まれた一角に昭和60年開館。
 館内入口:2007年7月21日から9月2日まで開催。
館内入口:2007年7月21日から9月2日まで開催。
 宣伝広告:村山壬子郎はマッチ業界の実力者、轟嘉兵衛の勧めにより明治31(1898)年に苫小牧で素地製造場を興した。(広告は明治36-37年時)
宣伝広告:村山壬子郎はマッチ業界の実力者、轟嘉兵衛の勧めにより明治31(1898)年に苫小牧で素地製造場を興した。(広告は明治36-37年時)
 村山マッチ小函素地工場:明治36(1903)年には4工場、従業員300人を数える大工場となる。しかし、明治43(1909)年になると経営不振に陥り神戸の良燧合資会社に経営権を譲り渡す。(写真は明治40年錦多峰)
村山マッチ小函素地工場:明治36(1903)年には4工場、従業員300人を数える大工場となる。しかし、明治43(1909)年になると経営不振に陥り神戸の良燧合資会社に経営権を譲り渡す。(写真は明治40年錦多峰)
 丸木製軸工場:苫小牧のアッペナイ地区にあったマッチ軸木工場。明治37(1904)年に笠原格一、酒井茂樹により設立され、従業員94人をかかえていた。(写真は明治40年頃)
丸木製軸工場:苫小牧のアッペナイ地区にあったマッチ軸木工場。明治37(1904)年に笠原格一、酒井茂樹により設立され、従業員94人をかかえていた。(写真は明治40年頃)
マッチの発明
会場は3つのテーマに分かれ、最初の展示は火を起こす技術の変遷を縄文、弥生時代にかけて、「火きり」と呼ばれる木の台座を錐のような棒でこすり出す単純な方法や舞切り式火起こし器の実物展示で見ることが出来る。 その次には、火打ち石から出た火花を火口に移し火種とする「燧(ひうち)」という方法の紹介から初期に発明された摩擦マッチ、黄燐マッチ、そして現在使われている赤燐を箱の側面に塗った「安全マッチ」までの解説がされている。
こうして、日々の生活において危険をともなう火を容易に起こすことを可能にしたマッチの発明は画期的なことといえる。 この19世紀の大発明はヨーロッパが先頭を切り、1827年にイギリスの薬剤師ジョン・ウォーカーが摩擦マッチを発明したのだが、発火具としては火付きが悪く、悪臭も放つ欠点があった。その後、発火点の低い黄燐を使った摩擦マッチが1831年、フランスの化学者ソーリアによって発明された。この黄燐マッチはヨーロッパ全土に普及し需要は一気に延びたが、黄燐の持つ毒性が深刻な健康被害をもたらし、さらに発火温度の低さからわずかな衝撃でも発火したり、自然発火による火災事故を併発する大きな社会問題にまでなっていった。 そこで諸問題の欠点を一気に解決したのが発火温度が高く、毒性もない赤燐の発見である。 1955年にスウェーデン、イェンシェピング社のルンドストレームが燃焼剤(塩素酸カリウム等)と発火剤(赤燐)をマッチ棒の先と外箱の側面とに分けた分離発火型のマッチを開発し、「安全マッチ」として特許を取得し、これ以後、スウェーデンは世界を席巻していくこととなった。現在も世界一のマッチ生産国である。 こうした西洋化学の発展によってヨーロッパのマッチ産業は盛んとなり、世界へ向けて絶対的優位な立場を築きあげていった。
 舞切り式火起こし器:火をおこす簡単な方法は木の台を錐のような棒を手で揉む方法でかなりの時間を要した。そこで考え出されたのが錐の先端と横木に三角形に紐を張って効率良く回転させる舞切り式のものが考案された。
舞切り式火起こし器:火をおこす簡単な方法は木の台を錐のような棒を手で揉む方法でかなりの時間を要した。そこで考え出されたのが錐の先端と横木に三角形に紐を張って効率良く回転させる舞切り式のものが考案された。
 ドロノキ、エゾマツ:マッチ軸木には白楊樹のドロノキ(左)、小函の原料にはエゾマツ(右)を素地とした。素地は半製品の状態で室蘭港から神戸へ移出していた。
ドロノキ、エゾマツ:マッチ軸木には白楊樹のドロノキ(左)、小函の原料にはエゾマツ(右)を素地とした。素地は半製品の状態で室蘭港から神戸へ移出していた。
 マッチ発火薬品:頭薬には燃焼剤として硫黄(イオウ)、酸化剤として塩素酸カリウム、側薬には発火剤として赤燐が使われている。
マッチ発火薬品:頭薬には燃焼剤として硫黄(イオウ)、酸化剤として塩素酸カリウム、側薬には発火剤として赤燐が使われている。
国産マッチの開発
さて、展示の次のコーナーでは明治から昭和初期に至るまでの国内外に出回った国産の商標マッチ、広告マッチが日本燐寸工業会と筆者の所蔵のなかから3000点ほど紹介されている。 販売を目的とした商標マッチにはマッチメーカー各社が独自の図案を描き、商標として登録をすることでデザイン盗用の防止策とした。 宣伝を目的とし、無料で配った広告マッチは明治26(1893)年に登場するが、その宣伝効果が認められ流行りだしたのは大正期に入ってからとなる。ともにマッチ箱に貼られたラベルのデザインに趣向を凝らした。 国産マッチ製造の最初は明治8(1875)年、清水誠なる人物が文部省の留学生としてフランスで学んだ化学の知識を基に黄燐マッチの開発に成功を収め、翌9(1876)年、東京本所柳原町にマッチ工場「新燧社(しんすいしゃ)」を設立し、販売を開始した。
 特別展示室:明治から昭和初期までの登録商標マッチを展示。奥の壁面には昭和初期の広告マッチラベル。(日本燐寸工業会、筆者 蔵)
特別展示室:明治から昭和初期までの登録商標マッチを展示。奥の壁面には昭和初期の広告マッチラベル。(日本燐寸工業会、筆者 蔵)
 経木マッチ箱:明治後期の経木製の登録商標マッチ箱そのままの形状で展示。(筆者 蔵)
経木マッチ箱:明治後期の経木製の登録商標マッチ箱そのままの形状で展示。(筆者 蔵)
 登録商標マッチラベル:明治から昭和初期までの登録商標マッチラベルを時代別に展示。(日本燐寸工業会 蔵)
登録商標マッチラベル:明治から昭和初期までの登録商標マッチラベルを時代別に展示。(日本燐寸工業会 蔵)
その後、新燧社の成功により名古屋、大阪、神戸などの全国各地でマッチ会社が興り、次第に品質もともなった製品は輸出用として海外へ行き渡ることとなる。 明治37(1904)年から大正8(1919)年までの繁栄期には生糸、綿花、お茶とともに輸出の花形産業にまで発展していった。特に輸出港であった神戸港に近い神戸、姫路は地の利を活かせたうえに乾燥工程が多いマッチの製造に適した、雨が少なく温暖な「瀬戸内海性気候」であったこと、さらに居留地に住む華僑や外国人の貿易商と組むことで中国を筆頭にインド、東南アジアへの輸出を容易にした。 最盛期には神戸が生産額の80%を占める国内最大のマッチ生産地となり、最も成功を収めたひとり、瀧川辨三は国内シェアの70%を占有し「日本のマッチ王」と呼ばれた。
 宣伝広告:日本のマッチ王と呼ばれた神戸の瀧川辨三が興した瀧川燐寸、良燧合資会社の宣伝広告。(明治36-37年時)
宣伝広告:日本のマッチ王と呼ばれた神戸の瀧川辨三が興した瀧川燐寸、良燧合資会社の宣伝広告。(明治36-37年時)
 登録商標マッチラベル:明治から昭和初期までの登録商標マッチラベルを図像別に展示。(筆者 蔵)
登録商標マッチラベル:明治から昭和初期までの登録商標マッチラベルを図像別に展示。(筆者 蔵)
 マッチ会社ポスター:明治から昭和初期までのマッチ会社発行の宣伝ポスターを展示。(筆者 蔵)
マッチ会社ポスター:明治から昭和初期までのマッチ会社発行の宣伝ポスターを展示。(筆者 蔵)
こうしたマッチ産業の発展にともないマッチラベル(燐票)の商標印刷も初期の木版、銅版印刷からマッチの需要増加に応えられる活版印刷機が導入され、明治22(1889)年頃からは西洋から伝搬した木口木版が普及し、電気版(電胎凸版)と呼ばれる原版複製技法を駆使して精緻な多面刷り印刷が行われるようになった。 さらに明治後期になると石版印刷が商標類にも普及し、4~7度刷りの印刷を施した美的でカラフルな燐票(りんぴょう)はマッチの顔となり、マッチの繁栄を支えていった。まさに「マッチはラベルで売れた」所以である。
広告マッチの隆盛
最後の三番目のテーマは、1970年代喫茶店全盛期、苫小牧在住のコレクターが蒐集した当地の広告マッチの数々が当時の懐かしい街並みの写真とともに展示されている。 全国的な喫茶店ブームとなった70年代には苫小牧市では191店、北海道内では約2500の喫茶店があり、名曲喫茶、ジャズ喫茶、純喫茶など現在のカフェ感覚とは違う雰囲気をマッチ一箱の存在が当時を想い起こさせてくれる。苫小牧市での喫茶店は昭和57(1982)年の213店をピークに減少し、現在では60店ほどのようである。 敗戦後、世界に築きあげていた販路を一挙に失ったマッチ産業は国内に販路を拡大していく戦略に転換を余儀なくされ、広告マッチに力を注ぎ込んでいった。
 苫小牧市内喫茶店のマッチ箱:昭和70年代に流行った名曲喫茶やジャズ喫茶とともに当時待ち合わせや食事を済ませた後の憩いの場として親しまれていた喫茶店文化の象徴としてマッチは存在していた。(鈴木耕榮氏 蔵)
苫小牧市内喫茶店のマッチ箱:昭和70年代に流行った名曲喫茶やジャズ喫茶とともに当時待ち合わせや食事を済ませた後の憩いの場として親しまれていた喫茶店文化の象徴としてマッチは存在していた。(鈴木耕榮氏 蔵)
 苫小牧市内の広告マッチ:昭和70年代からの喫茶店、飲食店のマッチの数々を当時の街並みの記録写真とともに展示。(鈴木耕榮氏 蔵)
苫小牧市内の広告マッチ:昭和70年代からの喫茶店、飲食店のマッチの数々を当時の街並みの記録写真とともに展示。(鈴木耕榮氏 蔵)
その結果、販売用の商標マッチの厚みを半分ほどにしてポケットにも納めやすくした寸二(平型)サイズの形態を基本とし、コート紙に平版オフセット印刷機で刷ったラベルを貼ったものが宣伝効果もともなった上に日常でも重宝したことで昭和40年代まで大いに流行り、喫茶店や街の商店から企業、銀行、デパートまで多くのマッチが自由に作られ、宣伝のために配られた。 マッチ箱の材質は昭和30年代までは経木と呼ばれたマツ材を薄く板状にした木製でその表面にラベルを糊付けしていたが、以後は、ボール紙にラベルのデザインを直接印刷し、貼る手間を省いた形状に変貌し現在に至っている。 広告マッチと並行して街の煙草屋や荒物屋などで売られていた販売用の商標マッチは、現在では需要の減少から煙草屋にも置かれなくなり、スーパーマーケットか100円ショップでささやかに売られている様はマッチ愛好家としては寂しい限りである。
 家庭用徳用マッチ箱:昭和30年代からの大箱の徳用マッチを展示。(筆者 蔵)
家庭用徳用マッチ箱:昭和30年代からの大箱の徳用マッチを展示。(筆者 蔵)
ほどよい不便
こうして国産としては133年の歴史を持つマッチは今や最盛期の30分の1にまで落ち込んでいるが、使い捨てライターとは違い、マッチは環境にやさしいエコ商品であることに気づいてもらいたい。 マッチ用原木は雑木として扱われているポプラ属のアスペンを適材としており、環境破壊にはつながらない。また、有害な薬品は含まれてなく、排水も無害、マッチ箱も古紙90%以上を使用している。 マッチは今では日常品としての役割を終えたかのような感もあるが、安くて便利な商品がものの進化の積み重ねで次々と開発されていくなか、マッチのようなアート感覚も兼ね備え、ちょっとした暖かみを持った「ほどよい不便」もあっていいのではないかとこの度の展覧会を観てつくづく思う。