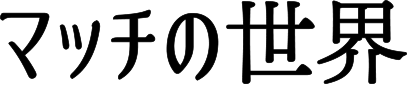マッチの歴史
HOME > バーチャルミュージアム > マッチの歴史 > スウェーデンマッチの日本上陸
昭和2年(1927)当時貿易商社の大手である鈴木商店が破綻して、マッチ業界に少なからずの影響を与えた。鈴木商店はロシアの極東沿海州の白楊(軸木用木材)を一手に取り扱っていたが、鈴木商店の経営悪化にともない、輸入途上の白楊木材が差し押さえられる事態となった。当時の日本燐寸同業組合聯合会の理事森一郎と船井長治が銀行や関係木材会社と折衝して、木材の確保に成功している。また鈴木商店の倒産にともない、その影響で帝国燐寸株式会社は工場閉鎖となり、従業員300人が失職を余儀なくさせられた。
前年スウェーデン燐寸は日本の全燐寸会社との合弁に失敗したが、昭和2年以後は各個別の会社との折衝を試みた。当時日本一のマッチ会社である東洋燐寸株式会社と具体的な折衝に入り、東洋燐寸、日本燐寸、公益社を一丸とした大同燐寸株式会社の設立となった。新会社の社長は東洋燐寸社長の瀧川儀作が就任したが、出資株の半数はスウェーデン燐寸から出ている。
大同燐寸の規模は工員数は7,000名、マッチ工場15ヶ所、印刷工場2ヶ所、軸木工場3ヶ所、生産能力月産3万マッチトンであり、国内の65%を押さえているが、将来は大同系で90%を支配して日本の市場を支配する計画であった。更に、蒲田、諌山両工場が合弁、朝日燐寸株式会社を設立して、大同燐寸の傘下に入った。スウェーデン側はさらに中小のマッチ会社と合弁の話を進めて、朝日燐寸に組み入れてその支配下に置いた。スウェーデン燐寸は世界各国で過度競争に悩むマッチ業界に対し、豊富な資金力をバックに世界を支配した典型を日本でも実現したことになる。
昭和3年頃から中国の日貨排斥、発展途上国の自国生産、各国の輸入制限を目的とした高率輸入関税、スウェーデンマッチの東洋への進出で、日本のマッチの輸出が極端に減少していった。それに対し各社がマッチの販売を国内向けに重点を置いたため、過度競争はますます激しくなった。大同燐寸は大幅な値下げでシェアを伸ばそうとしたため、業界の不況はますます深刻を極めた。
昭和4年(1929)になると、スウェーデンマッチは、大同燐寸の入江工場(神戸市)に自動燐寸製造機5台及び箱詰機、箱貼機を設置して、昼夜交代で大量生産に入った。このため大同系のマッチ会社と非大同系の中小マッチ工場との競争はますます激しさを増した。
昭和5年(1930)には、大同燐寸と三井物産との間に燐寸商標を巡る一大係争事件が起きた。三井物産では明治29年(1896)以来フィリピンおよび南洋方面に月琴印商標のマッチを輸出、販路拡張に努めてきた。しかるにスウェーデン燐寸系のフィリピン燐寸会社が三井物産の月琴印の商標を模したマッチを盛んに売り出した。商標の違いは月琴の中央にある三井を意味する三の字の代わりにフィリピン燐寸のPMCが印刷されているだけである。三井物産がその模造商標の出所を調査したところ、神戸市にある大同燐寸の印刷工場で印刷されていたことが判明。三井物産は神戸地方裁判所に告訴し、検事局が大同燐寸工場等を立入り検査して、模造月琴印商標800万枚を証拠品として押収した。

三井物産の商標(左)とフィリピン燐寸の商標(右)
月琴印の商標の商標権は三井物産株式会社と日本燐寸製造株式会社の共有になっていることから問題を複雑にした。その後、三井物産と大同燐寸およびスウェーデン燐寸との間で合議した結果、示談が成立、スウェーデン側は三井物産が主張の商標の権益を認め、三井物産はスウェーデンおよび大同両社の体面を尊重し譲歩して告訴を取り下げたといわれている。
昭和6年(1931)になるとマッチ業界の不況はさらに深刻となり、賃金引下げや工場閉鎖が相次いで発生した。日本の需要の7、8割を制覇した大同燐寸も経営が苦しくなり、その上、昭和7年(1932)には重役間で内紛問題が起こった。結局東洋燐寸系の瀧川儀作社長が退いてスウェーデン燐寸系のマグナッソンが社長に就任した。
ところが、スウェーデン燐寸本社の首脳者クロイガーが資金難から昭和7年3月にパリで自殺した。クロイガーの資金源は帳簿を虚構し、架空のマッチ利権を担保とし、イタリア政府の公債偽造、ドイツ政府債の二重抵当など、一連の詐欺行為によるものであった。その後大同の経営が苦しくなり、5・6月に至り休業を余儀なくされた。大同燐寸はスウェーデン本国からの支援が絶たれて、経営が成り立たず、遂に久原系(日産系)の鮎川義介に買収された。
昭和7年、日本燐寸工業組合では不況打開には生産統制しかないとして、政府に申請して生産数量制限が公布された。生産割当については、大同・朝日系マッチ工場の休業の期間をどう見るかで問題を残したが、大同系が月産15,400マッチトン、大同以外が33,000マッチトンで始めることになった。昭和9・10年になると市場が安定し、日産系の休業していたマッチ工場も順次再開し、これらの工場も黒字がでるようになった。